JR東日本からの運賃改定申請が、2024年12月に国土交通省に提出されました。申請がそのままの内容で認可され、2026年3月に運賃改定が実施されます。
旅客運賃の上限額については、鉄道事業法により国土交通大臣による認可が必要です。そのため、鉄道会社から申請が出された時点で運輸審議会に諮問されます。そして、答申が出されるまでの過程でパブリックコメントの募集や公聴会が実施され、国民から広く意見を募ることになっています。
今回の答申では、JR東日本の申請内容がそのまま適切であるとされました。しかし、当該答申では以下のような問題点に触れられていません。
- 運賃の引き上げによって社会全体の経済的負担が増す問題
- 運賃制度の大幅な変更が伴うことで制度がかえって複雑化する問題
- 列車の運行本数削減やみどりの窓口縮小といったサービス面の問題
ユーザーの意見を聴く機会が設けられているにもかかわらず、出された意見が答申に直接反映されていません。そのようなことは、果たして社会に受け入れられるのでしょうか。

鉄道事業法では総収入が総括原価を超えない限り認可しなければならないとされています。そのため、ユーザー目線での問題点が適切に反映されない点が課題です。残念ながら、答申が出されるまでの過程が形骸化していると言えるでしょう。
この記事では、JR東日本から2024年12月に出された運賃改定申請が認可相当であるとされた理由や、答申が出されるまでの過程をつぶさに見ていきます。そして、パブリックコメントとして寄せられた意見の数々から、申請内容(運賃制度やサービス面)に関する課題を考察していきたいと思います。
- 運賃改定申請を認可する過程では、政府が旅客サービス面の問題に介入できないこと
- 国土交通省から出された指針により、通算加算方式の採用が避けられないこと
- 通勤経路の変更や通勤定期券の事前購入等、ユーザーにとっての自衛策があること
JR東日本の運賃改定が認可相当とされるまでの経過

JR東日本(以下「会社」)から運賃改定のための申請が国土交通省に提出され、運輸審議会での審議を経てから答申が出されるまでの経過を、最初に振り返ります。
今回の運賃改定については社会に与える影響が非常に大きいことから、注目を集めました。
運賃改定の申請
鉄道旅客運賃については公益性が強いため、運賃の制定や変更に当たって国が関与することになっています。鉄道事業法による規制があるため、鉄道事業者は運賃や一部の料金について国の認可を受けなければなりません。
JR東日本管内の運賃改定について、2024年12月16日に会社から国土交通省に申請が出されました。当該申請と同時に、この件が運輸審議会に諮問されました。
鉄道事業法第16条第2項に基づき、想定される総収入が適正な原価に適正な利潤を加えたもの(総括原価)を超えないことが審査されます。
今回会社から提出された運賃改定の具体的な内容については、以下の記事をご一読ください。
パブリックコメントの募集
運輸審議会においてこの事案が審議されるにあたって、同年12月中にパブリックコメントが募集されました。
JR東日本という日本最大の鉄道会社による制度変更を伴う大々的な申請であったため、社会からの関心が高い状況でした。結果的に、国土交通省には191件もの意見が寄せられました。
パブリックコメントとして寄せられた様々な意見の全文など、具体的な内容が答申後に公開されました。
運輸審議会の公聴会
鉄道運賃の認可にあたって、運輸審議会は公聴会を開くことができるとされています。今回の事案においても、2025年2月27日に公聴会が開催されました。
筆者は参加しなかったのですが、あらかじめ申し込めばオンラインで公聴会を視聴可能でした。会社側からの説明があった後、一般から募集された公述人3名による公述が行われました(うち1名は代読)。
当日は、会社の従業員と思われる人や一般の鉄道ファンが自らの意見を述べた模様です。公述書に目を通した限りいずれも反対意見で、総括原価算定の問題点や旅客サービス面の問題点が挙がりました。
答申
運輸審議会において数回の審議を経て、同年4月1日に答申が出されました。この答申では会社から提出された申請内容がそのまま認められる形で、認可が適当であるとされました。
この答申が出たことによって、2026年3月に運賃改定が行われます。結果的には会社が提出した内容通りに運賃改定が行われることになりますが、社会に受容されるか否か注意深く見守りたいです。
運輸審議会から出された答申の内容

ここでは、運輸審議会から出された答申の内容を見ていきましょう。
答申の主文と理由
結論としての主文には、旅客運賃の変更を認可することが適当であると記載されています。会社から提出された内容がそのまま認可相当と答申された形です。
電車特定区間および山手線内の運賃区分を廃止し、幹線に統合することで、普通運賃と定期運賃を合わせて平均7.1%の引き上げとなります。
運賃が認可されるための条件は、旅客運賃の上限による総収入(上限運賃)が、能率的な経営のもとにおける適正な原価に適正な利潤を加えたもの(総括原価)を超えないことです。
今回の申請内容における総収入が、適正な総括原価よりも約91億円不足する見込みであり、その収支率は99.8%と推定されます。上述した条件を満たすため、認可することが適当であるとされました。

ユーザーから経済的負担の増加やサービス低下への懸念が挙げられているにもかかわらず、法律上の要件を満たすため認可しなければならないということです。
要望事項
パブリックコメントや公聴会で得られた意見や審議を踏まえ、答申には要望事項が記載されています。
今回の運賃改定が認可された背景として、コロナ禍以降の行動変容の影響が考慮されています。しかし、想定通りに需要が推移するか乖離が生じるかを見守る必要から、期限に関する条件を付けることを要望しました。
また、前述した電車特定区間および山手線内の運賃区分の廃止に関して、その必要性や合理性についてユーザーに周知するよう求めました。
法的な要件を満たすからと言ってそのまま認可するわけではなく、会社にはしっかりと要望していく姿勢が見られます。

それでは、ユーザーからの意見であるパブリックコメントの内容から、どのようなことが具体的に懸念されているのかを見ていきましょう!
パブリックコメントの内容
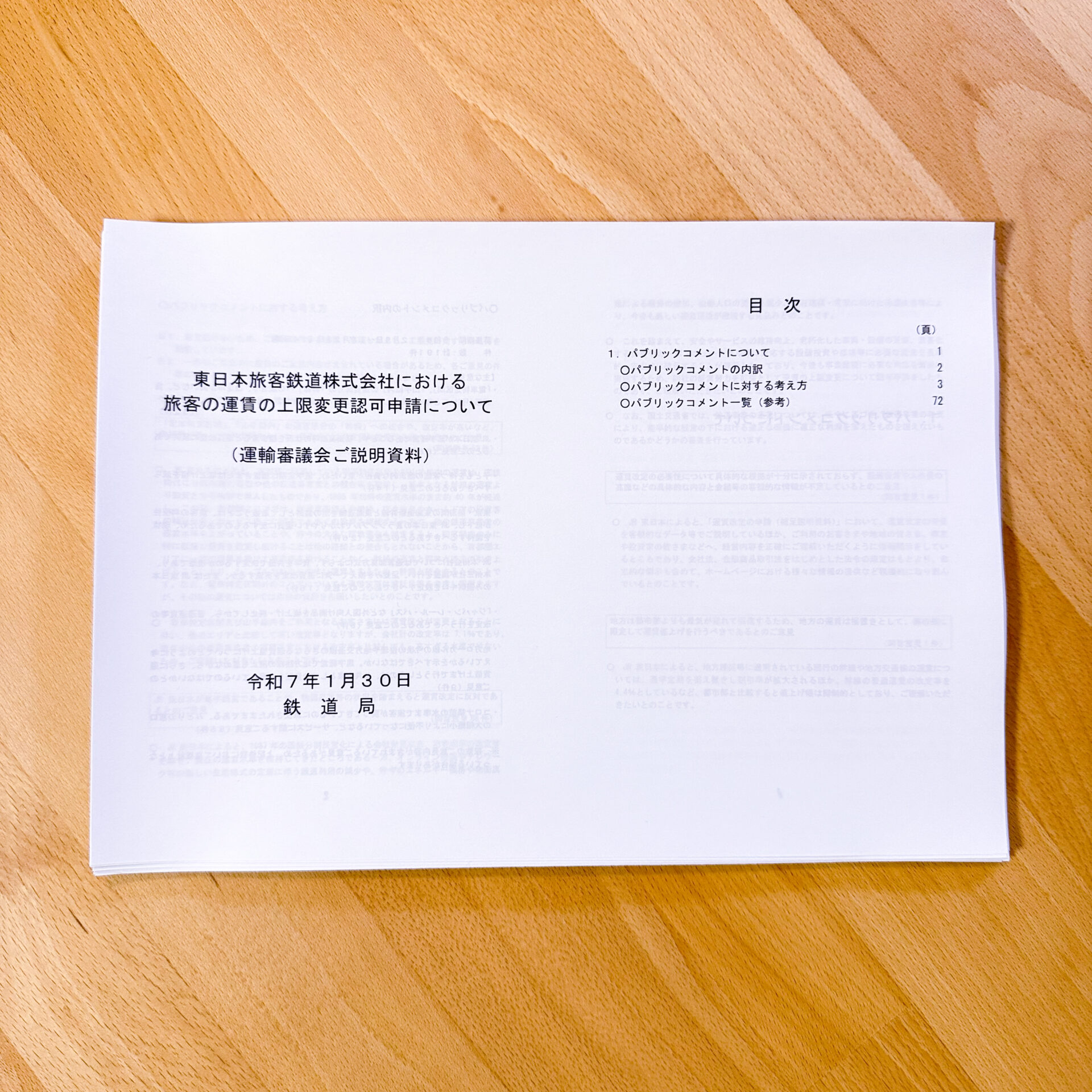
答申が出された後に開示されたパブリックコメントには、191件のコメントがそのまま掲載されています。パブリックコメントに対する会社の考え方を含めると、全体で173ページに及ぶ膨大な資料です。
寄せられた意見の大半は、会社への批判的な意見や懸念でした。運賃改定には、大勢が反対しています。相次ぐ輸送障害やサービス品質の低下から社会の関心が非常に高く、多くの意見が寄せられたと言えるでしょう。

個々の意見には会社からの回答が付いているのですが、通り一遍な内容というのが筆者の率直な感想です。
ここでは、寄せられた意見の中でも10件を超える主な意見をご紹介します。
- 電車特定区間・山手線内の運賃区分の廃止
- 業績が増収増益で黒字経営であること
- 通学定期に対する配慮
- 通算加算方式の適用について
- 東京駅・熱海駅間の別線扱い
- 列車の運行本数が少ないままであること
- みどりの窓口の営業縮小
また、寄せられた意見の中には、パブリックコメントの制度自体への注文も見られました。
経済的負担面
運賃の引き上げによって、ユーザーにとっては直接的に経済的負担が増加します。
電車特定区間・山手線内の運賃区分の廃止
電車特定区間・山手線内の運賃区分が幹線の運賃区分に統合されることなりますが、東京地区においては引き上げの幅が急激です。
改定率が高く、負担感が強いため、段階的に実施すべきではないかという意見が見られました。この点に関しては運輸審議会においても影響が強いとされ、要望事項として答申に盛り込まれたと思われます。
業績が増収増益で黒字経営であること
運賃改定の申請が出された時期の会社の業績は、増収増益で黒字経営が確保されている状況でした。
2025年4月末に開示された2025年3月期の会社決算によれば、親会社株主に帰属する当期純利益は2242億円でした(前期から14.2%増加)。このように業績が順調に伸びていることを踏まえ、株主への増配が行われました。
このような状況では、運賃の引き上げに反対する声が多く上がることは自然なことでしょう。
通学定期に対する配慮
今回の申請では、幹線区間の通学定期については変更がありません。
しかし、電車特定区間・山手線内の運賃区分の廃止による影響は、通学定期を利用する学生にも必然的に及びます。通勤交通費は企業から支給されるためともかく、通学定期の代金は家計から支出されます。
そのため、通学定期については値段を据え置いてほしいという声が多く上がっていました。
運賃制度面
JR東日本管内で大がかりな運賃改定が行われる関係で、JR他社にまたがって乗車する場合の運賃制度に手が加えられます。
通算加算方式の適用について
JR東日本区間とJR他社区間をまたがって乗車する場合、全区間の営業キロ(運賃計算キロ)に基づく基準額に、JR東日本乗車区間の距離に応じて加算額が設定されます。この制度変更によって、実務面で運賃計算が複雑になります。
本州3社で足並みをそろえて一斉に運賃を引き上げるべきといった声や、擬制キロ(運賃を割り増しするために設定する営業キロ)を設定すべきだという声が見られました。
東京駅・熱海駅間の別線扱い
JR東海が運営する東海道新幹線と、JR東日本が運営する在来線の東海道線を別線扱いし、後者の経路では加算額が適用されます。
現在は幹在同線であるため、どちらの経路を取っても運賃は同額です。しかし、今回の運賃改定によって、経路によって運賃に差が出ます。
「シンプルな運賃体系を目指す」と言いながらかえって複雑になるといった声や、現状維持するべきであるといった声が多く見られました。
旅客サービス面
鉄道会社への意見を直接国に上げられる機会は、滅多にありません。そのため、パブリックコメントにはサービス低下を懸念する声が多く寄せられました。
列車の運行本数が少ないままであること
2020年に起こったコロナ禍によって乗客が大きく減少した際、列車の運行本数が大幅に削減されました。しかし、コロナ禍が終了した現在においても列車本数が回復しておらず、減便された状態が続いています。
一例として、日中時間帯の山手線の列車運行本数については元に戻らず、混雑が増した状況です。列車を増発してサービス水準を元に戻してほしいといった声が多く見られました。
みどりの窓口の営業縮小
みどりの窓口がコロナ禍を契機に大きく減少し、社会問題になりました。これは、昨今のJR東日本のサービス低下を物語る典型的な事例です。
会社側は当面の間縮小を続けず、現状維持を図るとしています。しかし、一度減ったものが元に戻ることは考えにくく、ユーザーにとって負担であることには違いありません。
パブリックコメントの在り方に関する意見
前述した通り、運賃改定の認可には見込まれる総収入が総括原価を上回ってはならないという条件が付きます。ただし、鉄道事業法上はこの条件を満たす限り、運賃の変更を認可「しなければならない」ことになっています。
国土交通省が審査するのはこの点に限られるため、サービス面の問題点が顧みられることはありません。このような状況を懸念する声が見られました。
様々な意見が出されているにもかかわらず、鉄道事業者や国の言い分だけが通っています。そのため、パブリックコメントが単なる通過儀礼と化しているのではないかと指摘されていました。
筆者としても、会社の事業全体を審査できない鉄道事業法には限界があり、パブリックコメントや公聴会が形骸化しているのではないかと考えます。

パブリックコメントの中に見られた運賃制度面の問題を、さらに深掘りしていきます!
運賃制度面での問題点を深堀り

今回の運賃改定申請の内容に含まれる「通算加算方式の導入」および「東京駅・熱海駅間の別線化」に関しては、懸念する意見が多いです。
それぞれの観点について、ここで詳しく掘り下げていきます。
通算加算方式に関する問題点
JR会社間においては、会社ごとに運賃計算を区切るのではなく、全区間の運賃計算を通算して基準額を求めます。会社ごとの賃率の差については、各社区間の距離に応じて加算額を求めます。
全区間を「通算」し、加算額を「加算」するということで、通算加算方式と呼ばれます。
通算加算方式による現場の負担増
通算加算方式を採用することによって各社への運賃配分が明確になる一方、運賃計算が煩雑になることが難点です。まさに、現場泣かせの方式であると言えるでしょう。
JR東日本がJR他社にまたがる境界駅は、以下の12駅です。
- 北海道:新青森駅
- 東海:熱海駅・小田原駅・国府津駅・新横浜駅・品川駅・東京駅・甲府駅・辰野駅・塩尻駅
- 西日本:上越妙高駅・南小谷駅
現行で通算加算方式が導入されているJR北海道・JR四国・JR九州における境界駅の数が少ないにもかかわらず、運賃計算は難解です。境界駅の数がこのように多いJR東日本が通算加算方式を本格導入したら、運賃計算の複雑さは並ではありません。
通算加算方式の足かせ
このような問題点に対し、会社は以下の指針により通算加算方式としなければならないとしています。
2001年にJR会社法が改正されたのと同時に「新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する指針」が国土交通省から発出されました。その指針により、本州3社間をまたがって乗車する場合の運賃計算に関し、次の点を守ることが強制されることになりました。
- 全区間の距離を基礎として運賃および料金を計算すること
- 全区間の距離に応じて運賃を低減させること
前者が今回問題になっている「通算加算方式」で、後者が「遠距離逓減制」と呼ばれるものです。
この指針が出されてから今回の運賃改定までの間に、25年が経過しました。この指針が出された頃には、JR東日本が通算加算方式を導入するとは想定していなかったはずです。
この指針があるために、今回の運賃改定にあたって他の方式を採用できず、通算加算方式を適用せざるを得ません。指針で「当分の間配慮すべき」とはいえ、25年間で社会情勢は大きく変わりました。この指針の在り方が改めて問われるでしょう。
遠距離逓減制の詳細については、以下の記事をぜひご一読ください。
東京駅・熱海駅間の別線化に関する問題点
東京駅から熱海駅までの経路として、以下の2通りがあります。
- 東海道新幹線経由(JR東海)
- 東海道線経由(在来線:JR東日本)
それぞれ運営する会社が異なりますが、この区間が幹在同線であることが国によって認可されています。これによって、きっぷを変更することなく他経路を取れる点がユーザーと現場双方にとって便利です。
しかし、今回の運賃改定でこの区間が別線扱いとなり、経路によって運賃額が異なることになります。ユーザーにとって利便性が低下し、運賃制度がかえって「シンプル」ではなくなるという指摘は的を得ているのではないかと考えます。
この取り扱いが始まると、熱海駅・新横浜駅・品川駅・東京駅での区間変更の申し出が増えることが想定されます。在来線乗車に変更する場合運賃を追徴することになりますが、駅で手続きすることになるため、現場への負担が増えるはずです。

以上の内容を踏まえ、JR東日本管内の運賃が引き上げることによって生じる影響を考察していきます。
運賃が引き上げられることによる社会への影響

このように、JR東日本管内の運賃が東京地区を中心に大幅に引き上げられることにより、ユーザーのみならず社会に大きな影響がもたらされます。
一方、会社が志向している株主への配当増加が社会全体の利益と相反し、一部の資本家を利する結果となるのではないでしょうか。
鉄道輸送の公益性と上場企業の責務とのバランスをいかに取るか、非常に難しいところです。ここでは、運賃引き上げによる社会への影響についてお話を進めます。
ユーザー・一般企業にとっての負担増
答申には、普通運賃が7.8%、通勤運賃が12.0%の引き上げになる旨が記載されています。電車特定区間と山手線内の運賃区分が幹線に統合されることで、当該区間の引き上げ幅は見かけ上の数値を大幅に上回ると考えられます。
| 乗車区間 | 普通運賃 | 改定率 | 通勤定期 | 改定率 | 備考 |
| 東京駅・新宿駅間 | 210円→260円 | 23.8% | 6,290円→7,840円 | 24.5% | 旧山手線内完結 |
| 東京駅・大宮駅間 | 580円→620円 | 6.8% | 16,610円→17,970円 | 8.1% | 旧電車特定区間完結 |
| 東京駅・熊谷駅間 | 1,170円→1,230円 | 5.1% | 31,180円→32,780円 | 5.1% | 旧電車特定区間・幹線またがり |
いずれも、通勤定期の利用が多い区間です。通勤交通費については一般企業の負担であることから、人件費の増加に直接つながります。商品やサービスへの価格転嫁や、雇用への悪影響が懸念されるところです。
このように見ると、ユーザーにとって直接負担増となるばかりでなく、一般企業にも経費増の圧力がかかります。
株主(投資家)にとっての利益増加
一方、会社は株主への還元充実をうたっています。
前述した通り、会社の2025年3月期決算では、当期純利益が前期と比較して14.2%増加しています。順調に増収増益を果たしているため、剰余金が増配される見込みです(直近の配当予測よりも1株当たり8円増配)。
会社が目指す配当性向30%は、一般の上場企業と遜色がありません。ここで忘れたくないのは、会社の中核である運輸事業が高い公益性を持っていることです。
決算資料を見ると、ユーザーの増加により運輸事業単独で黒字です。不動産事業や物販事業の収益から運輸事業に内部補助することなく、仮に分社化しても独立して会社を運営できます。
公益性が高い事業を営利事業として運営すると、利潤を増やすために自ずとコストを削減する流れに傾きます。実際に、パブリックコメントに挙がっていた列車の運行本数の減少やみどりの窓口の減少と言った面で弊害が顕在化していることから、これが明らかではないでしょうか。
値上げやサービス低下の形でユーザーや一般企業が負担して生じた利潤が、株主配当として資本家に還流しているのです。
国による関与の在り方
このように、公益性の高い鉄道運輸事業をめぐっては、ユーザーと鉄道事業者の利害が真っ向から対立します。そこで、鉄道事業を監督する国土交通省が鉄道事業者をいかに管理するかが問われます。
JR東日本を含む本州3社については2001年にJR会社法の適用から除外され、経営の自主性が高まりました。その反面、鉄道事業を運営するにあたって、確実に利益を上げる点で経営責任が問われます。
コロナ禍に直面するまでは、公益性を有する鉄道会社としてユーザーとの関係には問題ありませんでした。しかし、コロナ禍を契機に、旅客サービス面でのコストカットが急速に進み、社会問題化しました。
このような状況であるにもかかわらず、国土交通省はユーザーの声に耳を傾けることなく、事業者であるJR東日本に寄り添っているように思えるのは、筆者だけでしょうか。
実際に、今回の答申が出されるまでの過程において、パブリックコメントで収集したユーザーの声に対して積極的に関与した様子はありません。運賃改定申請にあたって、総収入が総括原価を超えない点だけにしか関与できないのは、鉄道事業法の限界です。
JR東日本のサービス低下につながった元凶は、政府による行き過ぎた規制緩和であると考えますが、いかがでしょうか。
運賃引き上げから身を守るための対策

このように、社会への影響が大きい運賃引き上げがそのまま実施されようとしています。最後に、我々自身で準備できる対策に軽く触れます。
- 定期券の事前購入:運賃改定前日に6か月通勤定期券を購入することによって、値上げの影響を半年間先延ばし
- 通勤交通費の削減:リモートワークを取り入れることで通勤交通費を削減
- 通勤経路の見直し:他路線が利用可能な区間では経済的な経路を選択することを検討
例えば、東京メトロは運賃引き上げを行わないため、運賃を節約するために有効に活用したいです(一定程度JRから逸走が発生)。
まとめ

JR東日本から出された運賃改定申請が運輸審議会において認可相当であるとされたため、会社が提出した申請内容のままで運賃改定が実施されることになりました。
東京地区の電車特定区間と山手線内の運賃区分が廃止され、幹線の運賃区分に統合されることにより、実質的に大幅な引き上げとなります。特に通勤定期の改定率が大きく、一般企業には経済的負担が重くのしかかります。
JR他社またがりの場合、通算加算方式によって加算額を算出し、基準額に加算します。境界駅が多く、運賃計算実務が複雑になるため、本来望ましくありません。しかし、2001年に国土交通省から出された「新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する指針」によって、通算加算方式としなければなりません。
その他にも、東京駅・熱海駅間の別線化によるユーザーや現場の混乱が想定されることや、列車の運行本数、みどりの窓口に関するサービス低下の問題が残ります。
運賃引き上げによって得られた利潤が設備投資や旅客サービスに還元されるか、我々は監視する必要があります。会社は株主への還元を強化する意向ですが、配当性向が過度に増加しないよう見守りたいです。
この記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました!
参考資料
● 国土交通省 運輸審議会ウェブサイト 2025.5閲覧(以下同じ)
● 国土交通省ウェブサイト「新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する指針」
● JR東日本「運賃改定申請のお知らせ」特設サイト
● JR東日本ニュースリリース「2025年3月期決算短信」2025.4.30付
● JR東日本 アニュアルレポート2001
当記事の改訂履歴
2025年8月02日:初稿 最新修正
2025年5月05日:当サイト初稿





コメント